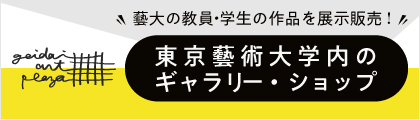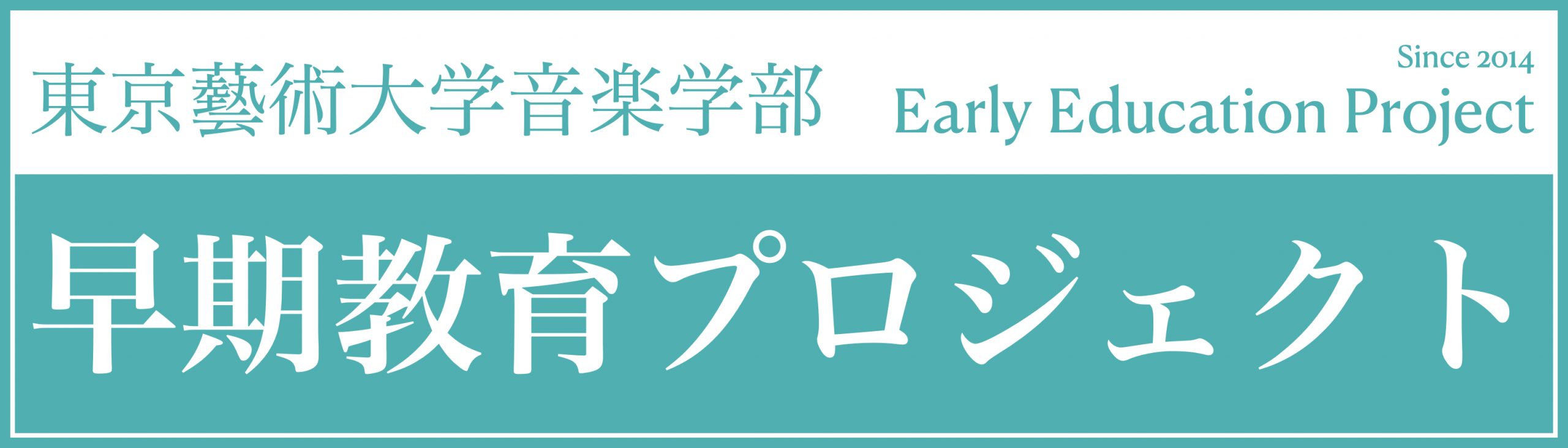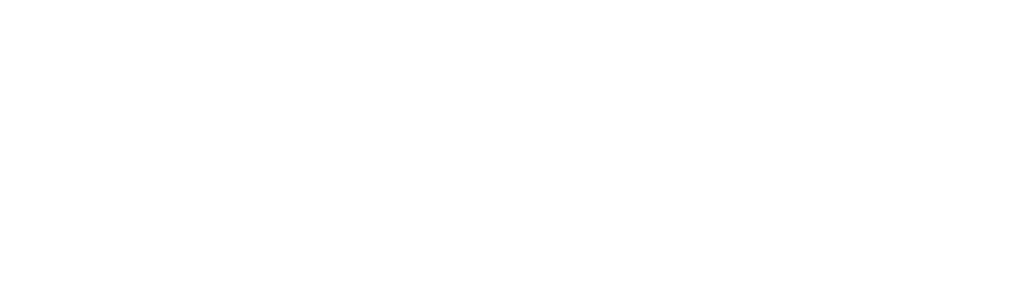- 大学概要
- 学部?研究科?附属機関?センター等
- 展覧会?演奏会情報
- 広報?大学情報
- 学生生活
- 卒業生の方へ
- 一般?企業の方へ
- 教職員の方へ
- 入試情報
- 藝大に寄附をする

第八十六回 石原孟 「2004年からの振り返りと今」
藝大の絵画科日本画に入学したのは2004年、学生としては2013年博士課程まで過ごし、その後助手、非常勤講師、
私が入学した時の日本画の世界は制度としての「日本画」、日本画とは何かなどが盛んに議論された後という印象がありました。振り返ると60年代からの構造主義やポスト構造主義の発想の延長に日本画という言葉やジャンルへの問いがあったように感じられます。
そんな言葉の上での「日本画」の議論は、後に学んでいくことになりますが、入学し当時の自分にとっては直接的な関係はあまり感じられず、ただ単純に絵を描こうという感覚で取り組んでいました。
日本画の授業は大きな課題が設定され、見た目は非常に簡潔なカリキュラムです。「風景」、「人物」、「自由制作」など大きな題目があるだけです。大きな課題の設定の下で、描きたい対象や視点、表現の独自性を探って行きます。
また岩絵具という素材に触れることが日本画科の大きな特徴です。チューブ状の絵具ではなく鉱物が粉砕された物質感の強い素材です。これを膠という接着剤と混ぜて画面に定着させていきます。至って単純なモデルのように感じられる表現形式ですが、大きな工夫の余地があり、またある程度思い通りに使えるまで時間がかかります。元の絵の具自体は美しいのですが、絵画として表現していく際の適切な使い方が悩みどころです。
自分自身の表現は現在もこうした単純であることの難しさと向き合いながら進んでいるようです。
前期授業では担当する第二研究室で毎年行う企画展示「素描展」

2025年 素描展 陳列館での自作の展示の様子
写真(トップ):大学院修了制作のとき。2013年、上野校
【プロフィール】
石原孟
東京藝術大学 美術学部絵画科准教授
2013年 東京藝術大学大学院美術研究科博士後期課程日本画研究領域修了
博士(美術) 創画会正会員
第8回東山魁夷記念日経日本画大賞展(2021年)
現在日本画研究会(2022年、2024年)
2022年から2025年まで、武蔵野美術大学通信教育課程、女子美術大学にて非常勤講師。
風景や動物をテーマにし、近年は色に関心を持って制作している。